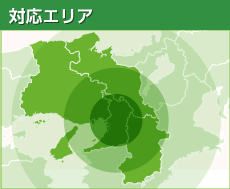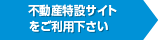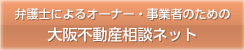遺留分侵害額請求と権利濫用
遺留分は権利として法律上認められたものですが、場合によっては、信義則違反、権利濫用などにより権利行使が認められないことがあります。
東京高裁平成4年2月24日判決・判例タイムズ803号236頁
被相続人母と同居した長男夫妻が感情的に対立し不和になったことから、長男夫妻の依頼に基づき、他の兄弟の了解のもとに、娘Y夫妻が自己が漸く確保した環境のよい公社住宅の優先使用権を放棄して母と同居し、約21年間の長期にわたり母を養育看護したが、その間において、母の遺産である宅地賃借権を等価方式により宅地交換取得する等の交渉過程において、弁護士の助言を得て、権利関係の明確化の関係もあって、兄弟特に長男と念入りな了解を受け、母の宅地所有権を娘Yに単独相続させる旨の遺言についても兄弟全員から権利主張をしない旨の書面の交付を受け、しかも家屋新築に際しては母の便宜を図っての設計により兄弟の求めた会社に建築注文をする等の配慮を払った等の事案において、兄弟の娘Yに対する遺留分減殺請求権の行使は信義誠実の原則に反し、権利濫用に当たるとされました。
東京地裁平成11年8月27日判決・判例タイムズ1030号242頁
裁判上の和解において遺留分の放棄を約したにもかかわらず、家庭裁判所の許可を得ていなかった場合に、遺留分減殺請求権を行使することが信義則に反するとされました。
和解における遺留分放棄の合意は家庭裁判所の許可に代えうるか否か
民法が遺留分減殺請求の事前放棄を家庭裁判所の許可によらしめたのは、古い家長制度の因習のもと、長子でないものが不当にその相続権を事前に剥奪されることのないように慎重を期したためである。遺留分減殺の放棄は、もとより家庭裁判所の許可がなければ効力のない要式行為である。
したがって、本件和解における遺留分放棄の合意をもって家庭裁判所の許可に代替しうるという被告らの主張は採用できない。
遺留分減殺請求は信義則に反するか
本件和解により、亡Aは、土地に関しては、4分の1の持分、即ち、亡Bの相続によって得られる持分のみならず、亡Cが死亡した際の相続によって得られる持分もあわせて取得しているところであり、それゆえにこそ、亡Aは本件条項により、「亡Aは、将来、亡Cから受ける相続分に相当する財産を既に取得することを認める。」旨確認しているところである。そして、これに引き続いて、亡Aは、「将来相続分及び遺留分を請求しないことを約束する。」と規定しているところである。本件条項がその重要性からして、単なる例文などではないことは明白である。
そして、本件において亡Aの包括承継人であるXらが、家庭裁判所の許可の手続が履践されていないことを奇貨として、遺留分を行使することを認めるならば、本件和解の合意に反し、Xらに二重取りを許すことになり、著しく信義に反することになる。