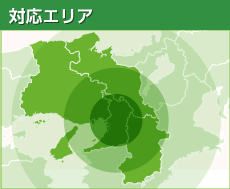10年経過後の遺留分侵害額請求権の行使
民法1048条では「遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。」と規定されています。
この「相続開始の時から10年」の期間は時効ではなく除斥期間と解されており、消滅時効とは異なり、中断がなく、当事者の援用も要しないとされています。
ところで、平成29年改正前の民法724条では「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。」と規定されており、この「不法行為の時から20年」も除斥期間とされていましたが、最高裁平成21年4月28日判決・民集63巻4号853頁は「そうすると、被害者を殺害した加害者が、被害者の相続人において被害者の死亡の事実を知り得ない状況を殊更に作出し、そのために相続人はその事実を知ることができず、相続人が確定しないまま上記殺害の時から20年が経過した場合において、その後相続人が確定した時から6か月内に相続人が上記殺害に係る不法行為に基づく損害賠償請求権を行使したなど特段の事情があるときは、民法160条の法意に照らし、同法724条後段の効果は生じないものと解するのが相当である。」と判断しています。
このように、除斥期間の場合であっても、特段の事情があるときは期間制限の効果は生じないとされたのです。
仙台高裁平成27年9月16日判決・判例時報2278号67頁
Xは、相続発生後、遺言書の存在を知ったが、これは無効だと説明されて遺産分割協議を続けたところ、10年以上経過した後、遺言は有効だとの見解を示され、更に半年以上経過してから遺留分減殺請求がなされたという事案において、Xは遺留分減殺請求権を行使することを期待できない特段の事情が解消された時点から6か月以内に同権利を行使したと認められないとされました。
民法1042条(※現1048条)後段の適用について
民法1042条(※現1048条)後段において、遺留分減殺請求権について、相続開始の時から10年間を経過したときに消滅する旨を定めた趣旨は、相続をめぐる法律関係の速やかな確定を意図することにあると解される。
上記規定の趣旨に照らしてみると、本件は、本件遺言に係る遺言としての権利主張が、相続開始の時から10年以上を経過した後になって行われており、その点において、既に法律関係の速やかな確定の要請に背反する事態が生じている事案である。さらに、本件遺言は、相続開始の時から約1年6か月後の時点で、その存在は明らかになっていたものの、同時に、遺言としての有効性について、無効であるとの見解が、具体的な理由付けを含めて専門家の見解として紹介され、Xを含む相続人全員が、これを信じて、以後、無効を前提として遺産分割協議が継続されていたという事情がある。そして、このような事情からすれば、上記見解が誤ったものであったことを踏まえても、Xにおいて、相続開始の時から10年間にわたり、有効な遺言が存在することを認識し得ず、その結果、遺留分減殺請求権を行使することを期待できない特段の事情があったと認めるのが相当である。以上のような事情の下で、相続開始後、受遺者による相続開始の時から10年間経過後の新たな権利主張が容認される一方で、これに対する遺留分減殺請求権の行使は一切許されないと解するのは、公平の見地から相当とはいえない。したがって、本件においては、民法1042条(※現1048条)後段の適用については、同法160条の法意に照らし、遺留分権利者であるXが、上記特段の事情が解消された時点から6か月以内に同権利を行使したと認められる場合には、Xについて、同法1042条(※現1048条)後段による遺留分減殺請求権消滅の効果は生じないものと解するのが相当である。
特段の事情について
Xは、本件遺言を遺言として無効であると信じていたのは、Aからその旨の説明があったことと遺産分割協議がこれを前提に継続されていたことによるものである。そうであるとすれば、平成23年10月30日の第4回の遺産分割協議において、Aが、本件遺言について、従前の見解を改め、専門家の見解を紹介して有効である旨主張するようになり、以後の遺産分割協議の継続を行わない意向を示した時点において、Xが本件遺言を無効と判断する事由は解消され、Xにおいて遺留分減殺請求権の行使を期待できない特段の事情も解消されたものと認めるのが相当である。
Xは、長年にわたって無効であることを前提とされていた本件遺言の有効性を上記Aの発言のみで判断することはできないと主張するが、本件遺言が遺言として無効なものと取り扱われていたのは、1回目の遺産分割協議におけるAの説明に基づくものであるから、これが撤回された以上は、本件遺言を遺言として無効であると解すべき積極的な根拠はなくなったと認めるのが相当であり、Xの上記主張は採用することができない。
そして、Xによる平成24年6月27日の遺留分減殺請求権の行使は、上記特段の事情が解消された平成23年10月30日の時点から6か月以上を経過した後のことであるから、結論的には、Xについて、同法1042条(※現1048条)後段による遺留分減殺請求権消滅の効果は生じないと解すべき事由は存在しないものと認めるべきである。