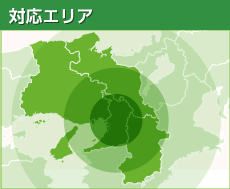相続放棄の熟慮期間の繰下げ
相続放棄申述についての3ヶ月の熟慮期間の起算点は、「被相続人が死亡した時」ではなく「自己のために相続の開始があったことを知った時」です(民法915条1項)。
従来、「自己のために相続の開始があつたことを知った時」とは、①被相続人死亡の事実のほか、②これにより自己が相続人になることを覚知したことを要し、かつ、これをもって足りるとされてきました。そのため、被相続人に対する債権者側において、被相続人の死亡後相続人の熟慮期間として定められている3ヶ月の期間内に、相続人に対し全く相続債務が存在する事実を知らせず、熟慮期間が経過するのを待って突如相続人に対し相続債務の支払を求めるという事例が続出しました(大阪高裁昭和54年3月22日決定・判例タイムズ380号72頁)。
これに対し、最高裁判所昭和59年4月27日判決が、相続放棄申述の熟慮期間の起算点を繰下げて相続放棄の申述を有効とし、3ヶ月の熟慮期間の起算点が繰り下げられる場合があることが認められました。
最高裁昭和59年4月27日判決・民集38巻6号698頁
「民法915条1項本文が相続人に対し単純承認若しくは限定承認又は放棄をするについて3か月の期間(以下「熟慮期間」という。)を許与しているのは、相続人が、相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った場合には、通常、右各事実を知って時から3か月以内に、調査すること等によって、相続すべき積極及び消極の財産(以下「相続財産」という。)の有無、その状況等を認識し又は認識することができ、したがって単純承認若しくは限定承認又は放棄のいずれかを選択すべき前提条件が具備されるとの考えに基づいているのであるから、熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知った時から起算すべきものであるが、相続人が、右各事実を知った場合であっても、右各事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。」
限定説と非限定説
最高裁昭和59年4月27日判決が「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じた」と表現しているため、熟慮期間の起算点を繰り下げることができるのは、相続人が「相続財産はまったく存在しない」と信じた場合に限るとする見解(限定説)と、積極財産が存在し、かつ、その認識があっても、相続財産が著しい債務超過であるとの認識を欠いていた場合(事実を把握していたならば相続放棄をするのが通常であると合理的に考えられる場合)にも熟慮期間の起算点を繰り下げるべきとする見解(非限定説)とに分かれています。
相続放棄申述の受理における審査
相続放棄申述がなされた場合、裁判所は、形式的要件(申述人が真の相続人であるかどうか、申述書の署名押印等法定の方式が具備されているかどうかなど)とともに、実質的要件(申述が本人の真意に基づいているかどうか、3ヶ月の熟慮期間内の申述かどうか、法定単純承認の事実の有無など)も審理し、受理するか否かの判断をします。
ただし、相続放棄申述の受理は相続放棄の効果を生ずる不可欠の要件であること(民法938条)、不受理の効果が大きいのにもかかわらず、却下審判に対する救済方法が即時抗告しかないのは、抗告審の審理構造からいって不十分であることから、熟慮期間内かどうかの要件を裁判所が実質的に審理すべきであるとしても、一応の審理で足り、その結果要件の欠缺が明白である場合にのみ申述を却下するべきであって、それ以外は同申述を受理するのが相当であるとする裁判例が多く見受けられます(福岡高裁平成2年9月25日決定・判例タイムズ742号159頁、大阪高裁平成14年7月3日決定・家庭裁判月報55巻1号82頁、東京高裁平成22年8月10日決定・家庭裁判月報63巻4号129頁)。ただし、仙台高裁平成4年6月8日決定・判例タイムズ844号232頁は、一般論としては同様の判断をしつつも、結論としては、相続放棄の申述が熟慮期間経過後のものであるとて、不受理とした原審判を維持しています。
熟慮期間繰下げに関する裁判例
熟慮期間の繰下げにつき、学説では、前記のとおり限定説と非限定説に分かれていますが、裁判例では、限定説か非限定説というよりも、個別の事案における結果の妥当性を重視しているように思われます。すなわち、裁判官が、相続放棄申述を受理すべき事案だと考えれば非限定説的な立場で、不受理とすべき事案だと考えれば限定説的な立場で判示しているということです。
もとより、個別の事案においては担当裁判官の価値観により結論が大きく左右されます。実務においては、このようなリスクを十二分に考慮する必要があります。
繰下げを認めた裁判例
仙台高裁決昭和59年11月9日決定・判例タイムズ541号238頁
被相続人は先妻との間に子供がいる男性と結婚しましたが、その子供たちとは養子縁組を行いませんでした。被相続人が死亡し、その兄弟姉妹が相続人となりましたが、兄弟姉妹は養子縁組をしていない子供たちが相続人になるものと誤信し、3ヶ月以内に相続放棄の手続をとらず、同期間の経過後に相続放棄の手続をとりました。家庭裁判所は相続放棄申述を不適法として却下したため抗告されたものです。
高裁決定は、民法915条1項所定のいわゆる熟慮期間は、原則として、相続人が、相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から起算すべきものであるが、相続開始原因たる被相続人の死亡等の事実を知っていても、自己の先順位者があると誤信していた場合には、未だ自己が法律上相続人となった事実を知ったとはいいえないと解すべきであるとして、原審判を取消し、差し戻しました。
尚、この事案は、後から借金が出てきたという事案ではなく、長年被相続人と生活し実の親子以上に手厚く被相続人を看護して子らに対する感謝の念もあって、同人らが被相続人の遺産を受け継ぎ、家業を守り育てて行くべきであると考え、各自の自由意思により本件相続放棄の申述をするに至った事案です。
大阪高等裁判所昭和61年6月16日決定・判例時報1214号73頁
相続放棄の申述が被相続人の死亡時から3ヶ月の期間経過後であっても、申述人において相続財産が全く存在しなかったと信じ、かつ、このように信じるにつき相当の理由を認めるべき特段の事情の主張があり、かつ、それが相当と認めうる余地のあるものについては、その実体的事実の有無の判定を訴訟手続に委ね、当該申述が真意に出たものであることを確認したうえ、原則として申述を受理すべきであるとし、相続放棄の申述を却下した原審判を差し戻しました。
神戸家裁昭和62年10月26日審判・家庭裁判月報40巻3号60頁
限定承認における共同相続人の一部の者による翻意は、合一の意見による申述であると信じて申立てをした他の共同相続人にとっては不測の事態となるから、その限定承認申述受理申立てが熟慮期間の経過後に却下された場合であっても、これに引き続いて改めて相続放棄申述受理の申立てをすることができるとされました。
広島高裁昭和63年10月28日決定・家庭裁判月報41巻6号55頁
被相続人の死亡の事実及び自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3ヶ月の熟慮期間経過後にされた相続放棄申述受理申立てを却下した審判に対する即時抗告審において、申述人らは被相続人と別居後その死亡に至るまで被相続人との間に全く交渉がなかったこと及び被相続人の資産や負債については全く知らされていなかったこと等によれば、申述人らが、被相続人の死亡の事実及びこれにより自己が相続人となったことを知った後、債権者からの通知により債務の存在を知るまでの間、これを認識することが著しく困難であって、相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当な理由があると認められるとして、原審判を取り消し、申述を受理させるため事件を原審に差し戻されました。
高松家裁平成元年2月13日審判・家庭裁判月報41巻9号120頁
昭和62年7月17日、債権者Xによる求償金請求事件の訴状を受け取ってから3ヶ月以内に相続放棄をせず、昭和62年12月16日の口頭弁論期日に受領した準備書面の副本を見て共同相続関係にあった他の相続人が相続放棄をなし、その結果、申立人の単独相続になったことを知って相続放棄申述を行った事案において、被相続人の債務が多額で、申立人と同順位の他の共同相続人全員が相続放棄をした結果申立人が負担することになる債務が拡張する場合には、申立人が、自己の負担する債務額として具体的数額を確知したときから起算して3ヶ月以内になした相続放棄の申述は適法であるとして、これを受理しました。
仙台高裁平成元年9月1日決定・家庭裁判月報42巻1号108頁
相続放棄申述の受理審判に当たっては、法定単純承認の有無、熟慮期間経過の有無、詐欺その他取消原因の有無等のいわゆる実質的要件の存否について、申述書の内容、申述人の審問の結果あるいは家庭裁判所調査官による調査の結果等から、申述の実施的要件を欠いていることが極めて明白である場合に限り、申述を却下するのが相当である。
大阪高裁平成元年11月27日決定・家庭裁判月報42巻5号71頁
相続人らが被相続人と同居していたことのみを理由に、被相続人死亡当時、相続人らが多額の債務の存在を知っていたものと推認し、本件相続放棄の申述が熟慮期間経過後のものであると即断してこれを却下した原審判を取消し、差し戻しました。
東京高裁平成元年12月8日決定・家庭裁判月報42巻5号74頁
家庭裁判所調査官による「債権者からの催告状況」の調査報告書などに基づき相続放棄の申述を却下した原審判に対し、原審が認定した事実の存在を相続人らが争っていることは明らかであるから、このような場合には、原審としては、単に被相続人の債権者からの事実調査等だけではなく、更に進んで相続人らからも審問その他の事実調査等をしたうえで本件に係る事実関係を把握し、これに対する判断をすべきであるとして、原審判を取消し、差し戻しました。
福岡高裁平成2年9月25日決定・判例タイムズ742号159頁
「家庭裁判所は、相続放棄の申述に対して、申述人が真の相続人であるかどうか、申述書の署名押印等法定の方式が具備されているかどうかの形式的要件のみならず、申述が本人の真意に基づいているかどうか、3か月の熟慮期間内の申述かどうかの実質的要件もこれを審理できると解するのが相当であるが、相続放棄申述の受理が相続放棄の効果を生ずる不可欠の要件であること、右不受理の効果が大きいこととの対比で、同却下審判に対する救済方法が即時抗告しかないというのは抗告審の審理構造からいって不十分であるといわざるをえないことを考えると、熟慮期間の要件の存否について家庭裁判所が実質的に審理すべきであるにしても、一応の審理で足り、その結果同要件の欠缺が明白である場合にのみ同申述を却下すべきであって、それ以外は同申述を受理するのが相当である。このように解しても、被相続人の債権者は後日訴訟手続で相続放棄申述が無効であるとの主張をすることができるから、相続人と利害の対立する右債権者に不測の損害を生じさせることにはならないし、むしろ、対立当事者による訴訟で十分な主張立証を尽くさせた上で相続放棄申述の有効無効を決する方がより当を得たものといいうる。そして、相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が相続人となった事実を知った時から3か月以内に相続放棄の申述をしなかったのが、相続財産が全くないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、右熟慮期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である」と説示し、本件では、3ヶ月の熟慮期間は、公正証書謄本が送達された日から起算されると認める余地があるから、本件相続放棄の申述はこれを受理するのが相当であるとして不受理とした原審判を取り消しました。
仙台高裁平成7年4月26日決定・家庭裁判月報48巻3号58頁
相続人らは、被相続人の死亡当時、被相続人名義の不動産が存在していたことは認識していたものの、被相続人の生前から、被相続人名義の不動産の一切を他の相続人である長男が取得することで合意していたことから、被相続人名義の不動産が相続の対象となる遺産であるとの認識はなかったとして、被相続人の死亡後1年9ヶ月余りを経過した後の相続放棄の申述を却下した審判原審判を取り消し、各申述を受理しました。
仙台高裁平8年12月4日決定・家庭裁判月報49巻5号89頁
家庭裁判所が相続放棄の申述を不受理とした場合の不服申立ての方法としては、高等裁判所への即時抗告だけが認められているにすぎず、その不受理の効果に比べて、救済方法が必ずしも十分であるとは言えないから、家庭裁判所において、その申述が熟慮期間内のものであるか否かを判断する場合には、その要件の欠缺が明らかであるときに、これを却下すべきであるとしても、その欠缺が明らかと言えないようなときには、その申述を受理すべきものと解するのが相当であり、このように解しても、被相続人の債権者は、後日、訴訟手続で相続放棄の効果を争うことができるのであるから、債権者に対して不測の損害を生じさせることにはならないとし、相続放棄申述を不受理とした原審判を取消し、差し戻しました。
大阪高裁平成10年2月9日決定・判例タイムズ985号257頁
一部の相続人に遺産の全部を取得させる旨の遺産分割協議がなされた後、予期に反する多額の相続債務があったとして、他の相続人からなされた相続放棄申述を却下した審判に対する抗告審で、分割協議が錯誤により無効となり、ひいては単純承認の効果も発生しないとみる余地があるとして、原審判を取り消して差し戻しました。
名古屋高裁平成11年3月31日決定・家庭裁判月報51巻9号64頁
相続人が被相続人の死亡時に、被相続人名義の遺産の存在を認識していたとしても、たとえば同遺産は他の相続人が相続する等のため、自己が相続取得すべき遺産がないと信じ、かつそのように信じたとしても無理からぬ事情がある場合には、当該相続人において、被相続人名義であった遺産が相続の対象となる遺産であるとの認識がなかったもの、即ち、被相続人の積極財産及び消極財産について自己のために相続の開始があったことを知らなかったものと解するのが相当であるとし、申述を却下した原審判を取消し、差し戻しました。
東京高裁平成12年12月7日決定・判例タイムズ1051号302頁
申述人は、被相続人が死亡した時点で、その死亡の事実及び申述人が被相続人の相続人であることを知ったが、被相続人の遺言があるため、自らは被相続人の積極及び消極の財産を全く承継することがないと信じたものであるところ、遺言の内容、遺言執行者であるA銀行の申述人らに対する報告内容等に照らし、申述人がこのように信じたことについては相当な理由があったものというべきであり、また、申述人は相続財産の一部の物件について遺産分割協議書を作成しているが、これは遺言において当然に他の相続人Bへ相続させることとすべき不動産の表示が脱落していたため、遺言の趣旨に沿ってこれをBに相続させるためにしたものであり、申述人において自らが相続し得ることを前提に、Bに相続させる趣旨で遺産分割協議書の作成をしたものではないと認められるから、これをもって単純承認をしたものとみなすことは相当でないとして、相続放棄申述を不受理とした原審判を取消し、差し戻しました。
福岡高裁平成16年3月16日決定・判例タイムズ1179号315頁
申述人は、平成15年1月ころには、被相続人が国に対し仮払金返還債務を負担していた事実や先順位の相続人らが相続放棄の申述をした事実を知っていたことが窺えるが、他方、申述人は、農林水産省の担当者から、次順位の相続人である申述人については、先順位の相続人が全員相続放棄をしたことが確認されれば、関係書類を送付するので、これを見て対応するようにとの説明を受けたというのであるから、申述人が次順位相続人として仮払金返還債務について相続開始の事実を認識するに至ったのは通知書の送付を受けた後であると認めるのが相当であるとし、相続放棄の申述を不受理とした原審判を取消し、受理しました。
名古屋高裁平成19年6月25日決定・家庭裁判月報60巻1号97頁
Xにおいて、被相続人に積極財産があると認識していたものの、被相続人が一切の財産を他の相続人に相続させる旨の公正証書遺言を遺していること等の事情からすれば、Xが被相続人の死亡時において、自らが相続すべき財産はないと信じたことについて相当の理由があったものと認めることができ、また、相続債務についても、その存在を知らず、債務の存在を知り得るような日常生活にはなかったと推認されることなどから、被相続人の連帯保証債務の支払を求める訴訟の訴状を受け取るまで、Xが相続債務について存在を認識しなかったことについても相当な理由があるから、民法915条1項本文所定の期間は訴状を受け取って相続債務の存在を認識した時から起算するのが相当であるとし、不受理とした原審判を取り消し、相続放棄申述を受理しました。
東京高裁平成19年8月10日・家庭裁判月報60巻1号102頁
相続人において被相続人に積極財産があると認識していてもその財産的価値がほとんどなく、一方消極財産について全く存在しないと信じ、かつそのように信ずるにつき相当な理由がある場合には、民法915条1項本文所定の期間は、相続人が消極財産の全部又は一部の存在を認識した時又はこれを認識し得べかりし時から起算するのが相当であるとし、不受理とした原審判を取り消し、相続放棄申述を受理しました。
仙台高裁平成19年12月18日決定・家庭裁判月報60巻10号85頁
未成年者である相続人の法定代理人(親権者母)が、被相続人である離婚した元夫の住宅ローン債務に係る同人の保証委託契約上の債務を連帯保証していた事案について、ローンに係る住宅は被相続人の両親も生活し、住宅ローン債務は離婚時の協議により被相続人又は被相続人の兄弟において処理することになっていたこと、被相続人死亡後の残債務は被相続人が加入していた団体生命保険によって完済されていると考えていたことなどの事情の下においては、債権者から主債務者の相続人に向けた照会文書を同法定代理人が受領するまで、同人が被相続人の債務があることなどについて十分な調査をしなかったことにはやむを得ない事情があったというべきであり、相続財産がないと考えていたことについて相当な理由があったものというべきであるから、上記照会文書の受領時から民法915条1項本文の熟慮期間が進行するとし、不受理とした原審判を取り消し、相続放棄申述を受理しました。
高松高裁平成20年3月5日決定・家庭裁判月報60巻10号91頁
相続債務について調査を尽くしたにもかかわらず、債権者からの誤った回答により、債務が存在しないものと信じて限定承認または放棄をすることなく熟慮期間が経過するなどした場合には、相続人において、遺産の構成につき錯誤に陥っているから、その錯誤が遺産内容の重要な部分に関するものであるときは、錯誤に陥っていることを認識した後改めて民法915条1項所定の期間内に、錯誤を理由として単純承認の効果を否定して限定承認または放棄の申述受理の申立てをすることができるとし、不受理とした原審判を取り消し、相続放棄申述を受理しました。
東京高裁平成22年8月10日決定・家庭裁判月報63巻4号129頁
原審・東京家裁平成22年3月8日審判(家庭裁判月報63巻4号134頁)は、地方裁判所から催告状の送達を受けた日以前に、それぞれが借地権を相続していること、滞納賃料等の支払を求めること、などを内容とする通知文書の配達を債権者から受けており、遅くともそのときまでには、被相続人が死亡し、自己が法律上相続人となったことおよび被相続人には相続財産(借地権及び負債)が存在することを知ったものと推認され、したがって、相続放棄の申述は熟慮期間経過後にされたことになるとして却下しました。
これに対し、高裁決定は、上記通知文書は特定郵便にて配達されたものであるところ、特定記録郵便は、書留郵便と異なり、受取人の郵便受箱に投函し、受取人の受領印やサインをもらわないというものであるから、配達したかどうかを事後的に確認する手段としては、その確実性に一定の限界があるというべきであって、抗告人の住居は集合住宅であるというのであるから、本件通知文書が誤配された可能性を完全に否定することはできないとして、原審を取消し、相続放棄の申述を受理しました。
東京高裁平成26年3月27日決定・判例時報2229号21頁
Xらは、被相続人が死亡した当時、被相続人の相続財産に不動産があることを知っていたものの、①被相続人の意向を聞いていたために、長男であるAがこの不動産等被相続人の相続財産を一切を相続したので、自らには相続すべき被相続人の相続財産がないものと信じていたことが認められる、②「遺産分割協議証明書」に署名押印し、Aに送付又は交付したことが認められるが、上記書面は、被相続人の相続財産の不動産についてAの名義に移転登記するためにAに送付等されたものであり、現実に遺産分割協議がされたものではないから、この書面の送付等をもって、自己のために相続の開始があったことを知ったものと認めることはできないから(この点に関する経過の詳細等については、訴訟が提起された場合にその訴訟手続内において判断されるべきである。)、その後、Xらが信用金庫に問い合わせること等により被相続人の信用金庫に対する貸金債務についての連帯保証債務が被相続債務として存在していることを知った日から熟慮期間が進行するとして、不受理とした原審判を取消し、相続放棄申述を受理しました。
福岡高裁平成27年2月16日決定・判例時報2259号58頁
相続人が相続財産の一部の存在を知っていた場合でも、自己が取得すべき相続財産がなく、通常人がその存在を知っていれば当然相続放棄をしたであろう相続債務が存在しないと信じており、かつ、そのように信じたことについて相当の理由があると認められる場合には、最高裁昭和59年4月27日判決の趣旨が妥当するというべきであるから、熟慮期間は、相続債務の存在を認識した時または通常これを認識し得べき時から起算すべきものと解するのが相当であるとし、不受理とした原審判を取消し、相続放棄申述を受理しました。
東京高裁令和元年11月25日決定・判例時報2450・2451号5頁
法定相続人Xらは、被相続人の固定資産税に関する市役所からの文書を受領してから3ヶ月経過後に相続放棄の申述をしたところ、原審は、相続放棄の熟慮期間を経過してされたものであるとして却下しました。これに対し、高裁は、申述の遅れは、相続放棄手続が既に完了したとの誤解や被相続人の財産についての情報不足に起因しており、Xらの年齢や被相続人との従前の関係からして、やむを得ない面があったというべきであるから、本件における民法915条1項所定の熟慮期間は、Xらが、相続放棄手続や被相続人の財産に関する具体的説明を受けた時期から進行するとして、原審判を取り消し、申述を受理しました。
繰下げを認めなかった裁判例
盛岡家裁昭和59年9月20日審判・家庭裁判月報37巻7号57頁
生前、第三者Xから建物の明渡訴訟を提起されながら、その後もこれを明け渡すことなく居住し続けてきた被相続人の死亡後、Xから相続人らに対し被相続人の不法占有期間中の損害賠償債務を相続したものとして、賃料相当分の損害賠償請求の訴えを提起されたため、相続人らが、民法915条所定の熟慮期間は訴え提起を知った時から起算すべきであると主張して、被相続人の死亡の事実を知ってから約140日後に相続放棄の申述を申し立てた事案です。審判は、被相続人に対する訴訟の結果は相続人全員が知っており、被相続人が建物に居住し、無償で不法占拠した結果、Xに賃料相当損害金債務を負っていたことを承知していたと認められるところ、相続人らには損害金債務につき免除を受けたものと勝手に思い込み、債務が存在しないと信ずるに至った経緯について重大な過失があるから、本件相続放棄の申述は、同条所定の熟慮期間経過後に、申し立てられたものであるとして、これを却下しました。
福岡家裁小倉支部昭和60年2月6日審判・判例タイムズ552号268頁
被相続人の死亡当事、その妻子である相続人らが、被相続人の事業経営に全く関与しておらず、積極、消極の相続財産の存在も全く認識していなかったとしても、その後、被相続人の債権者から、債務者被相続人に対する貸金債権についての承継執行交付金銭消費貸借契約公正証書謄本が相続人らに対して送達されているときは、相続放棄の熟慮期間は、おそくとも上記送達日から進行するものと解されるとして、相続放棄の申述をいずれも却下しました。
東京高裁昭和63年1月25日決定・東京高等裁判所判決時報民事39巻1~4号1頁
相続債務請求訴訟の訴状送達から3ヶ月以上経過した後の相続放棄の申述が却下されました。
仙台高裁平成4年6月8日決定・判例タイムズ844号232頁
相続人が相続開始後3ヶ月を経過して相続放棄の申述をした場合において被相続人の死亡時に被相続人に不動産があることを知っていたときには、その他の事情のいかんにかかわらず、家庭裁判所は右相続放棄の申述を却下することができるとしました。
高松高裁平成8年1月30日判決・訴訟月報43巻3号914頁
被相続人に相続財産が全く存在しないと信じるについて相当な理由があるとは認められないとして熟慮期間が被相続人の死亡時から開始するとされました。
静岡家裁平成9年10月20日審判・家庭裁判月報50巻6号97頁
申述人らは、被相続人について積極財産およびなんらかの消極財産が存在することを認識していたといわざるをえず、遅くとも被相続人にかかる遺産分割協議書作成の時から相続放棄の熟慮期間を起算すべきことになるとして起算時期から3ヶ月経過後の相続放棄の申述は受理されませんでした。
高松高裁平成13年1月10日判決・家庭裁判月報54巻4号66頁
申述人は、被相続人の相続財産として、土地、建物、預金があることを知っていたから、申述人は被相続人の死亡の日にその相続財産の一部の存在を認識したものといえるとし、被相続人の死亡の日から3ヶ月経過後になされた相続放棄の申述は不適法であるとしました。
大阪高裁平成13年10月11日決定・判例時報1770号106頁
被相続人の債権者から申述人に通知があった日から3ヶ月以上経過した後になされた相続放棄の申述が却下されました。
東京高裁平成14年1月16日決定・家庭裁判月報55巻11号106頁
相続人らは、被相続人が死亡した直後、被相続人が所有していた不動産の存在を認識したうえで他の相続人全員と協議し、これを長男である相続人Aに単独取得させる旨を合意し、同抗告人を除く他の相続人らは、各相続分不存在証明書に署名押印しているのであるから、相続人らは、遅くとも同日ころまでには、被相続人に相続すべき遺産があることを具体的に認識していたものであり、相続人らが被相続人に相続すべき財産がないと信じたと認められないことは明らかであるとし、銀行から訴えにより初めて請求を受けた日から3ヶ月以内に行った相続放棄の申述を不受理とした原審判を維持しました。
訴訟において相続放棄の効力が判断された事例
相続放棄の申述が家庭裁判所に受理された場合においても、相続の放棄に法律上無効原因が存するときは、後日訴訟においてこれを主張することができます(最高裁昭和29年12月24日判決・民集8巻12号24頁)。
相続放棄の申述を受理するか否かの審査に際しては、上述のとおり、一応の審理で足り、その結果要件の欠缺が明白である場合にのみ申述を却下するべきであって、それ以外は同申述を受理するのが相当であるとされていますが、債権者との間における訴訟においては、一応の審理ではなく、厳密に審理されることになります。
東京高裁昭和62年2月26日判決・判例時報1227号47頁
相続開始の約4ヶ月後になされた限定承認が熟慮期間徒過を理由に無効とされました。
福岡高裁昭和62年5月14日判決・判例タイムズ650号229頁
事実上の離婚状態にある妻において自ら引き取った未成年の子が夫の債務を相続しないと考えることは経験則に反するとして相続放棄申述および受理は無効としました。
大阪高裁平成2年11月16日判決・判例タイムズ751号216頁
Yは、被相続人である父の死亡当時、父に負債があることを知らなかったとはいえ、その当時から父に相続の対象となる不動産を含めた遺産があることを知っており、父が会社員ではあっても、その妻である母が営むブティックの営業に関し、その債務の保証をする蓋然性もあり、父死亡直後の葬儀に際しても母に負債がかなりあることを認識していたのであるから、父と同居していた母や兄に父の債務の有無を含めた相続財産の内容につき確認することも容易にてきたもので、相続財産内容の調査をYに期待するのが著しく困難であったともいい難いから、熟慮期間の起算点をYが父の死亡により自己が相続人となったことを知った時と異別に解すべき特段の事情は認められないから相続放棄の申述は無効であるとして、債権者XのYに対する請求を認容しました。
東京高裁平成15年9月18日判決・判例時報1846号27頁
債権者からの内容証明郵便につき、相続人が貸金債務の成立を疑い、あるいは、仮にそれが成立していたとしても、消滅時効が完成することによって貸金債務が消滅すべきものであると考えたとしても不合理であるとはいえないから、内容証明郵便の記載内容では、被相続人に相続財産の存在を認識させるには足りないとし、相続放棄申述を有効として貸金業者の請求を棄却しました。
大阪高裁平成21年1月23日判決・判例タイムズ1309号251頁
相続人Yが債権者Xの本件訴訟提起まで本件債務の存在を知らずにいて、かつ、本件債務を加えるとYが遺産分割協議によって相続した消極財産が積極財産を上回り、当事者間で遺産分割協議が無効になったとしても、Yは、遅くとも遺産分割協議の際には、被相続人に積極財産のみならず多額の債務があることを認識し、これに沿った行動を取っていたといえるのであって、このような事情に照らせば、Yについて,熟慮期間を本件訴状がYに送達された日から起算すべき特段の事情があったということもできないから相続放棄は無効であるとして、債権者XのYに対する請求を認容した原審判決を維持しました。