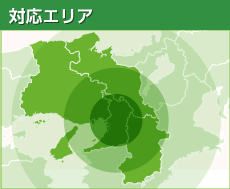財産取り込み(使途不明金)
「親が弱っていることをいいことに、他のきょうだいが親の財産を使い込んでいるようだ」、「相続が開始したところ、他の相続人が、被相続人の生前もしくは死後、被相続人の財産を使い込んでいる」というご相談を受けることがよくあります。
このような場合、紛争性が高くなり、ご本人間で解決することが困難と思われます。
当事務所にご依頼いただければ、適切な助言、サポートをさせていただきます。
相続開始前の対応
成年後見人選任の申立て
例えば、親の認知症が進行している状態であれば、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらうことをお勧めします。
このような紛争案件では、家庭裁判所は第三者の弁護士を成年後見人に選任するのが通例です。他のきょうだいは、成年後見人選任に抵抗する可能性が高く、成年後見人選任手続自体についても紛争となってしまいますので、弁護士を代理人として成年後見人選任の申立を行う必要も出てきます。
成年後見人が選任されれば、成年後見人が親の財産を管理し、もし、他のきょうだいが親の預金を無断出金していたのなら返還請求をすることになります。
成年後見人選任の申立てができない場合
親の判断能力が低下していないなど、成年後見人選任の申立てができない場合、現時点での対応は困難です。
相続開始後、相続人の資格で銀行から取引明細を取り寄せるなどして、被相続人の生前に他の相続人が財産を使い込んでいたか否かを調査し、相続手続の中で処理するしかありません。しかし、長期間経過してしまうと資料の入手が困難となりますので、この点にご留意ください。
相続開始後の対応
相続開始前に使い込んでいた場合
被相続人Aの生前に、相続人Y(Xのきょうだい)がAの財産(1000万円)を使い込んでいた場合、相続人Xはどのような手段をとることができるのでしょうか?
この場合、被相続人AはYに対して、不法行為に基づく損害賠償請求権もしくは不当利得に基づく返還請求権を有しており(1000万円)、被相続人の死亡によりXとYが当該請求権を相続します(各自500万円)。したがって、XはYに対し、損害賠償請求権もしくは不当利得に基づく返還請求権により500万円を請求することができます。この場合、遺産分割手続の中で、Aの生前にYが取得した1000万円を考慮して解決できる可能性もあります。
しかし、AがYに対し1000万円を贈与していた可能性もあり、そうすると、XがYに対し損害賠償請求権もしくは不当利得に基づく返還請求権を行使することはできず、遺産分割における特別受益の問題となります。あるいは、詳細は不明なので、とりあえず、遺産分割手続の中で特別受益の主張をするということも考えられます。
このように、民事訴訟で請求すべきか、遺産分割手続の中で清算を求めるのか、状況に応じて使い分ける必要があります。
相続人が相続開始前に被相続人に無断で預金を払い戻して領得していた場合における法律関係につき大阪高裁平成22年8月26日決定が述べていますのでご紹介します。
相続開始後に使い込んだ場合
被相続人Aが死亡した後、他の相続人YがAの死亡を銀行に伝えないまま、Aの名前で銀行から預金1000万円を引き出すということがあります。例えば、YがA名義のキャッシュカードを用いてATMから預金を払い戻した場合や、自らがAであると偽ってA名義の払戻請求書を作成し、銀行窓口で払戻しを受けた場合です。
この場合、他の相続人Xは、Yに対し、不法行為に基づく損害賠償請求権または不当利得返還請求権により500万円の請求を行うことになります。
このような場合、Xとしては、銀行から出金の際の資料を取り寄せ、何時、誰が出金したのかを調査する必要があります。そのうえで、他の遺産も存する場合には、当該出金分も考慮して遺産分割を行うか、あるいは、端的に、出金額の法定相続分の返還を求めるか検討すべきです。
なお、平成30年相続法改正により、①遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても共同相続人はその全員の同意により当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる(民法906条の2第1項)、②前項の規定にかかわらず共同相続人の1人又は数人により同項の財産が処分されたときは当該共同相続人については同項の同意を得ることを要しない(民法906条の2)、とされましたので、当該預金を引き出した以外の相続人全員の同意があれば、遺産分割手続の中で処理することも可能です。
コラム
サポート内容・費用
成年後見人選任申立て
| 着手金 | 30万円(税込33万円) |
|---|---|
| 報酬 | 20万円(税込22万円) |
| 実費 | 別途 |
※複雑または特殊な事情がある場合は別途見積致します。
損害賠償請求・不当利得返還請求
| 着手金 | 40万円(税込44万円) |
|---|---|
| 報酬 | 取得額の12%(税込13.2%) |
| 実費 | 別途 |
※複雑または特殊な事情がある場合は別途見積致します。
遺産分割調停・審判
| 着手金 | 40万円(税込44万円) |
|---|---|
| 報酬 | 取得額の8%(税込8.8%) |
| 実費 | 別途 |
※複雑または特殊な事情がある場合は別途見積致します。